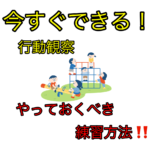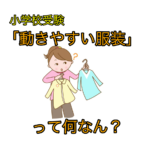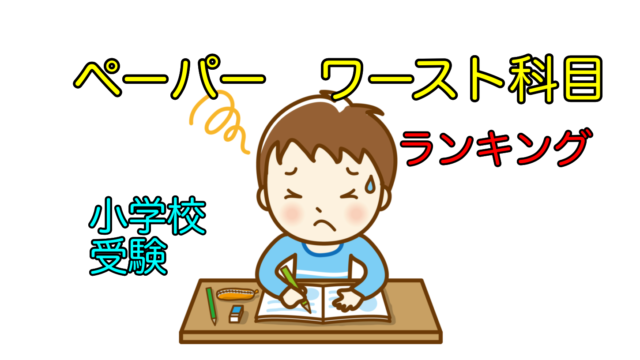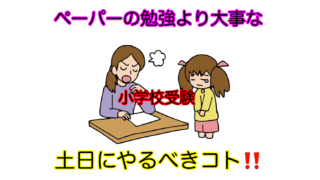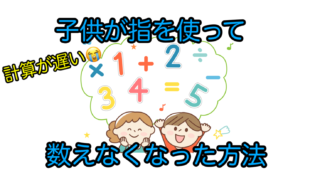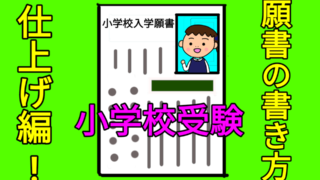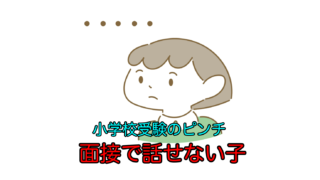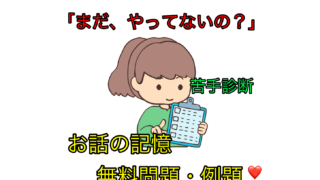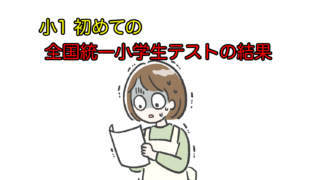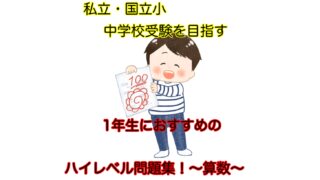今日は小学校受験でとても重要な「行動観察」の対策。でもどうやって練習したらいいのかが分からない科目で、とても教えづらい科目なのに、テストの配点が高く、とても悩んでいるお母さまも多いのではないでしょうか?
そこで今日は、おぺりちゃんと私が実際にやった苦手な子でも出来る様になる自宅での練習方法についてお話します。
このブログを書いている私は小学校受験指導歴7年・私立小学校に通う娘のおぺりちゃん1年生を塾なし!ほぼ自宅学習で合格させたワーママです。こんな私が解説していきます。
小学校受験 行動観察
行動観察とは

小学校受験の行動観察のテストとは子どもが課題や決められた遊びをする中でお友達の中でルールを守り仲良く出来るか、自分の意見を言えるか、積極性、協調性などを試験官が見て採点していくテストです。筆記試験のペーパー試験と区別され、子どもの行動を見る科目です。
重要視される理由
この『行動観察』の試験はペーパー試験に比べ、年々重要視される傾向にあります。
・学校は入学後、トラブルを起こさない・どんなお友達ともお友達と仲良くできる子を求めています。近年いじめなどのトラブルは学校としても避けたいからです。
・学校はペーパーなどの勉強は入学後に学校で教えるのでそこまで完ぺきを求めておらず、行動観察のお友達と仲良くできる、ルールを守る、意見を言えるなどの能力は小さい頃からご家庭での教育が重要と思っているんです。勉強ばかりできる子ではなく人間の内面的な部分にも今後伸びる事ができそうな子かを重要視する傾向にあります。
年々配点が高くなる傾向
 以上の理由から小学校受験での行動観察の配点が年々高くなっています。小学校受験の全体的な傾向としても ペーパー < 行動観察 重視型の試験内容へと変化している学校が増え行動観察の配点も高くなってきています。
以上の理由から小学校受験での行動観察の配点が年々高くなっています。小学校受験の全体的な傾向としても ペーパー < 行動観察 重視型の試験内容へと変化している学校が増え行動観察の配点も高くなってきています。
また、行動観察の試験内容も、難易度が毎年高くなり、社会人の協調性・グループ研修にも出て来そうな、難しい内容の試験を5,6歳の子がやると言うΣ( ̄ロ ̄lll)
大人でも驚くような試験内容が近年出題されてきています。それほど行動観察は小学校受験では重要視されいる科目と言う事なんですね!
行動観察が苦手な子の原因と対策
ところが、、、行動観察は試験会場で初めてあうお友達と仲良くする。そして出題された課題をこなす。自分の意見を言うといった。さまざまな要素がつまった「小学校受験 最難関 の試験とも言えます。」ところが、自宅での練習ができない点や。人見知りな子は行動観察が苦手な子も多く、実は行動観察はペーパー以上に練習が大切なんです!!
行動観察対策・練習方法
行動観察のポイントを押さえよう
行動観察が上達するには3つのポイントがあります。まずは行動観察のポイントをしっかりと理解する事。この行動観察のポイントをまずおぺりちゃんにお話してから練習に取り組むように意識することがとても大切です。
次は、より具体的な行動観察の自宅での練習の進め方をご紹介します。
自宅でできる行動観察練習
ステップ1 行動観察の本を読む
 読むしかない!年少・年中・年長別!!『行動観察』におすすめの本☜
読むしかない!年少・年中・年長別!!『行動観察』におすすめの本☜
ルールを知ろう
行動観察の基本となるお友達と仲良くできる!まずはルールを知る事が大事です!年齢にあったお友達と仲良くする事が分かるようなの絵本を寝る前に読み聞かせをしていました。「こんな時はどうしたらいいかな?」と具体的なお友達との場面をお子さんと一緒に考えるのがおすすめです!
ステップ2 行動観察の問題集や過去問を解く
行動観察 問題集
次はさらに具体的な行動観察の問題集を使った練習をしました。行動観察とはどんな試験なのか、どんな事に気をつけたら良いのかなど具体的な行動観察の内容を知り自宅で事前に学習するのにピッタリです。
行動観察 過去問

また、行動観察の実際の試験に近い内容の問題にも目を通しておくようにしました。特に、志望校の過去問に目を通し、毎年どんな行動観察の試験が出題されているのか出題傾向は必ずチェックしておきましょう。
行動観察 教室・単発
ステップ3 より実践的な練習をする
習い事の単発・無料体験レッスンに行って見る
今はいろいろな習い事の1回だけの単発のレッスンや無料体験がありますよね。
この体験、実は「初めての場所」「初めて会う先生の指示に従う」「初めて会うお友達と仲良く同じことをする」と言う所が行動観察にとても良く似ています。
行動観察の復習方法
親子で一緒に様子を見る事が出来るので、どこが良かったのか・どこを直した方が良いのかを知る事ができます。お子様と一緒に直すべきところを確認・しっかり復習をすることも大切です。
ステップ4. 単発の行動観察対策・教室に行く
塾に普段通っていなくても、大手の塾で行動観察の単発での教室が開かれている所があります。
行動観察の仕上げ練習に受験が近くなった年長の時はこういった所に足を運んでみるとより実践に近い内容になっていますので経験しておくことで受験本番にお子様が緊張することなくスムーズに出来るのかなと思いました。
行動観察 服装
男の子
行動観察の服装は『動きやすい服装』を準備するようにと言われることが多いです。早めに行動観察に必要な服装をチェックし、準備してくように心がけましょう。
女の子
行動観察での服装や身だしなみは男の子に比べ、特に女の子が気をつけるべき点が多いです。詳しくまとめましたのでこちらもぜひチェックしてみて下さい!
まとめ
行動観察は小学校受験に限らず、子ども将来、学校・社会の中で、誰とでも仲良くする。協力できる。自分の意見を言う。と言った世の中を上手くわたっていく【生きる力】が身に付くそんな科目です。
ぜひ皆さんもお子様の【生きる力】が身に付く行動観察の対策、ぜひやってみて下さい(#^^#)
 ←こちらも併せてお読みください!(^^)!
←こちらも併せてお読みください!(^^)!