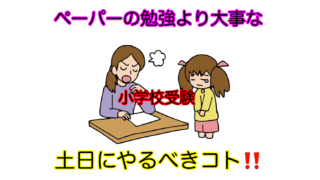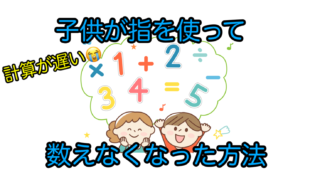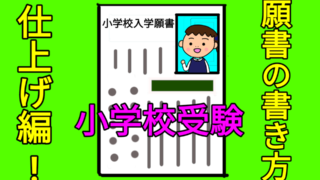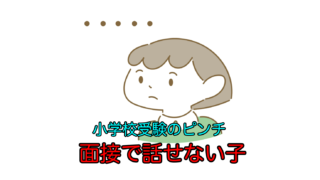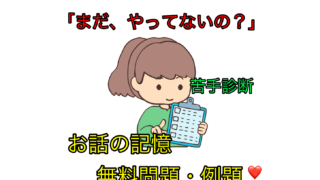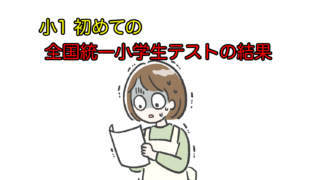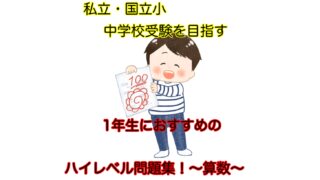おぺりちゃんもペーパーができなくて塾や模試でビックリ( ゚Д゚)する様な点数を取った事は多々ありました(笑)
ペーパーってなんだか毎日毎日机と紙に向かって楽しくないし、分からないと喧嘩になるしΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン 親子のモチベーションも下がる一方。小学校受験の対策を毎日ご家庭でやるのはお母さまをはじめとするお家の方は本当に大変ですよね。
今回は、ペーパーがなぜできないのかと実際におぺりちゃんがペーパーが得意になった方法についてご紹介します。
この記事を書いている私は小学校受験指導歴6年「娘のおぺりちゃんを小学校受験にほぼ自宅学習で合格させたワーママ」です。こんな私が解説していきます。
ペーパーが苦手・出来ない原因
子どもにあった教え方ができていない
そもそもお子様がペーパーができない原因は問題集選びや教え方を間違えていることが非常に多いです。まずはそこから見直しましょう。
基礎が分かっていない
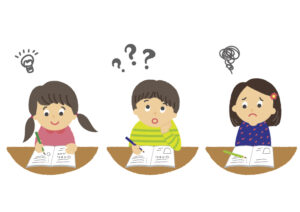
ペーパーができないポイント
お子さまが基礎の理解(インプット)ができていないのにいきなりたくさんの問題を解く事(アウトプット)をさせていませんか?
私も最初のうちおぺりちゃんにどうやって小学校受験のペーパーを教えていいのか分からずに、こぐま会の問題集とかをいきなりやらせていたんです。
まあ、今考えれば、そもそもその科目の理解(インプット)ができていないのに、問題を解く(アウトプット)なんてできるわけないのにそうやってしまっていたんですよね。。。
これでは小さな子にいきなり2輪の自転車をこげと言っているようなものです。まずは、ペダルのこぎ方を教えたり、バランスのとり方、スピードなど段階を踏んで教えてあげますよね?更に今はストライダーや変身バイクと言った更にすぐ自転車に乗れる方法があります。
ではどう教えたあげたらいいのか?もう、コツコツというよりストライダーや変身バイク的な(笑)この時代、受験のペーパーがすぐに楽しくできるようになる方法があります!
ペーパーの教え方
知育玩具を使う
まずは、おぺりちゃんと出来るだけペーパーの科目でも具体的な物を使って遊ぶ、見る、触ることで科目の基礎を理解させてあげていました。
例えば、
図形【点図形】におすすめの知育玩具
わごむパターンボード 公文出版
ペーパーの科目にあった知育玩具があれば紙で勉強するより具体物で遊ぶだけで理解がどんどんできます。
他にも小学校受験ペーパー対策におすすめの知育玩具☜詳しくはこちらの記事もお読み下さい
子どもにあった問題集を選ぶ
先ほども言いましたが、基礎の理解(インプット)ができていないのに、いきなり問題集を解く(アウトプット)の問題集をやらせたから、おぺりちゃんはペーパーが全く出来なかったんです。
まずは基礎の理解(インプット)ができる問題集で科目の基礎を分かるようにしっかりと教えてあげましょう!
step1 基礎の理解用(インプット)の問題集
おぺりちゃんが実際に使っていたのがこちらの問題集です。
合格する子は解き方が違う!!教え方が分かるお母さんのための問題集
この問題集は教え方に特化していて問題の隣に考え方が書いてあります。これを使えば教え方が分かるので、教え方が分からないお母さんでもお子様に基礎の理解(インプット)をスムーズにしっかりとさせてあげる事ができます。
合格する子は解き方が違う!!教え方が分かるお母さんのための問題集☜を実際に使ってみた感想・詳しい記事はこちら
step2 反復練習用(アウトプット)基礎編の問題集
先ほどインプットした基礎の知識を定着させるためたくさんの問題を解くことで反復練習(アウトプット)をする必要があります。
おぺりちゃんが基礎の反復練習(アウトプット)実際に使っていた問題集がこちらです。
step3 反復練習用(アウトプット)応用編の問題集
更に、小学校受験の模試や受験本番に近い問題は難しく基礎編だけでは足りないので応用編も問題を解きました。
おすすめの問題集はこちらです。
ペーパーが出来る様になるには段階を踏むことが大切です。
〇step1知育玩具などを使って具体物から理解する
〇step2基礎の理解用(インプット)の問題集やる
〇step3反復練習用(アウトプット)基礎編の問題集をやる
〇step4反復練習用(アウトプット)応用編の問題集で受験本番のレベルに!
子どもにあった志望校がしぼれていない
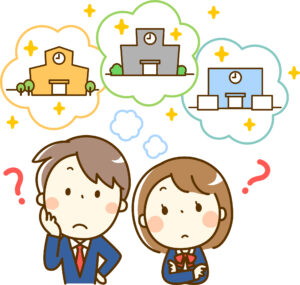 志望校はなるべく早めに絞った方が良いです。なぜなら志望校を絞る事である程度、出題傾向がつかめ、試験に出やすい「科目」を絞る事が出来るからです。小学校受験の科目は細かく分けると100科目以上に分けられます。そんな膨大な科目を全て完ぺきにしなくても志望校をしぼることでやるべき科目がわかり、無駄な勉強をしなくても良くなります。
志望校はなるべく早めに絞った方が良いです。なぜなら志望校を絞る事である程度、出題傾向がつかめ、試験に出やすい「科目」を絞る事が出来るからです。小学校受験の科目は細かく分けると100科目以上に分けられます。そんな膨大な科目を全て完ぺきにしなくても志望校をしぼることでやるべき科目がわかり、無駄な勉強をしなくても良くなります。
特に塾に通っていると色んな志望校のお子様向けなので自分の志望校なら勉強しなくてもいい科目まで広くやらないといけない傾向にあります。
また模試にもその傾向が言えます。模試の結果が悪いからと言って落ち込む必要は全くありません。注目すべきなのは志望校で出やすい科目が出来ているのか、出来ていないのかです。
親が過去問を読みこんでいない
小学校受験の志望校を決めたらまず1番最初にやるべきことは「過去数年分の問を買う」ことです。それを1問も見逃さずに徹底的に出題傾向をお家の方が分析してください。
そこで、その小学校が良く出す問題、必ず点を取るべき簡単な問題、難しすぎる捨て問など過去数年分の問題からお子様が必ず得意になるべき科目や難易度どこまで力を付けるべきなのかをしぼって学習計画を立ててあげることが出来ます。そうすることで、無駄な時間・無駄なお金、何よりお子様に無理に勉強させる負担が減ります。
そもそもペーパーがつまらない
モチベーションを保つ
小さい子が日々のペーパー学習を継続するのは本当に大変な事です。
プリントをやったら、がんばり表にシールやスタンプを押してあげるとそれだけで子どものモチベーションアップにつながります。
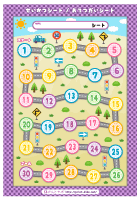
私はいつも「プリントキッズ」☜さんのこの表を印刷して使っていました。無料でダウンロードできます!
おぺりちゃんは30個シールが溜まったらごほうびをあげる約束をしていたのでそれを目標にペーパーの勉強を良くがんばっていました。
小学校受験とごほうびの末路☜詳しい記事はこちら
やりすぎない
平日はペーパーの勉強を1日30分やる!と決めたとします。
でも実際は子どもなので計画通りに行かない日ももちろんあります。そんな時は無理せずに枚数を減らしたり、1日お休みしたりと臨機応変に対応した方が上手く行くこともあります。
楽しくする
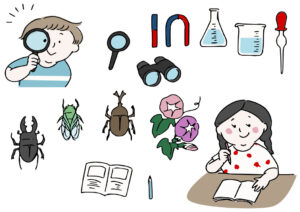 ペーパーの勉強の中にも遊びを取り入れるといつもの学習方法と違ってとても子供が喜んでくれます。たとえば理科で野菜の断面のプリントが出てきたら私はその野菜を実際におぺりちゃんと切って見たり、実験っぽくしたりした楽しく一緒に学ぶように心がけていました。
ペーパーの勉強の中にも遊びを取り入れるといつもの学習方法と違ってとても子供が喜んでくれます。たとえば理科で野菜の断面のプリントが出てきたら私はその野菜を実際におぺりちゃんと切って見たり、実験っぽくしたりした楽しく一緒に学ぶように心がけていました。
ほめる
とにかく褒めます(笑)褒めていればなんとかなる!と心に決めて( ´∀` )
答えが間違えていても、「考え方はとってもいいよ!」とか「問題文はよく理解してたね」とか「○が上手にかけているね」などとにかく何か良い所を見つけて褒めてあげましょう!
まとめ
小学校受験のペーパー対策
1.志望校は早めに絞る!
(ペーパーは範囲が広いので過去問を分析して出題される科目だけ完ぺきにするべし)
2.ペーパーの勉強は段階を踏む!
知育玩具とレベルにあった問題集を選ぶべし
3.日々のモチベーション管理!
ペーパーが長く楽しく続けられる工夫をすべし
小学校受験お話の記憶のコツ・教え方←こちらも併せてお読みください!(^^)!